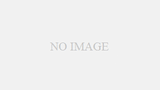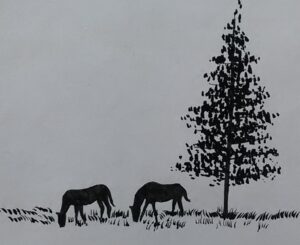
質問をする子はよく伸びます。昔,同じ問題を3回も4回も質問してくる女の子がいました。あるときさすがに「またこの問題?」と言ったら,にっこり笑って「分からないから聞いてるの」ときっぱり。「ああ,そうか」と私も笑いながら,何度目かになる同じ説明をくりかえしました。この子はだんだんと出来が良くなり(そのせいか質問の回数も減りました),見事桜蔭に合格しました。同じようなケースは他にもたくさんあります。質問する子ほどできるようになると,私は信じています。
質問することには別の利点もあります。子どもと教師のあいだに気持ちのつながりができるチャンスなのです。教える側は,「よくがんばっているね」「最近できるようになったんじゃない?」などと個人的に励ますことができます。そのような言葉をかけられて嬉しくない子はいないでしょう。説明した後で「ああ,よくわかった」と言われると,教える側も疲れが消し飛びます。「またね」と言ってアメ玉の1つでもあげたくなるというものです。
質問になかなか答えてくれない先生や,「こんなこともわからないのか」とか「前に教えたよね」などと言って,いかにも面倒だなという仕草を見せる先生ばかりの塾だったらやめたほうがいいです。私は若い頃,「自分の授業中の説明はかんぺきだ,きちんと聞いた子たちはよくわかったはずだ」などと思い上がっていたので,授業のあとに質問を受けると「授業を聞いていなかったのか」と思ったものですが,何度か説明しているうちに,誰でもわかるように教えることは簡単なことではない,と気がつくようになりました。同じことであっても,理解の仕方が子どもによって違うからです。したがって,同じ問題でも説明の仕方を変えて教えることはよくありました。授業で言った説明とは別の方法で説明するのです。わかってくれるまで。
分からないことを聞くのは当然の権利です。まったく恥ずかしいことではありません。まわりの大人は,できないことを叱るのではなく,わからないことを放置しないようにさせることが大切です。
家庭では,塾のノートやプリントの進み具合など,きちんとチェックするように親子で約束事として決めておきましょう。理解したかどうかをチェックし,質問をさせるためです。また,その質問に先生がどのように説明してくれたのか知ることもできます。本当に分かったのか,子どもに説明させるのも悪くない方法です。きちんと説明できたら「すごいね。わかったじゃない」と,たっぷりほめてあげてください。それができるような「親子仲が良い」関係ができれば,子どもは必ず伸びていきます。