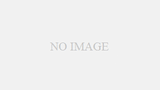どんな単純な式であっても数字を書く順番は大切です。たとえば小学生3年生レベルですが,「1袋に8つアメ玉が入っている袋が3袋あります。アメ玉は全部で何個ありますか」という問題では,8×3=24個と答えますが,3×8=24でも同じだと言う人がいます。大きな間違いです。アメ玉を数えるとき,8+8+8=8×3とするわけで,それは8個が3つあるという意味です。式には意味があるのです。3×8では意味をなしません。
別の例で言うと,「時速5kmで4時間進むと何km進みますか」という問題であれば,1時間に5km進むから,2時間だと5+5=10km,4時間だから5+5+5+5=5×4=20km進むと計算します。5kmが4つで20kmという意味です。これを4×5とすると,4が5個あるという意味になり,4時間×5=20時間という答えになってしまいます。
正しく考えていれば正しい式になります。いい加減な式を書いているようでは思考力は身に付きません。式を書くことは思考力を育てる意味合いもあるのです。
式を考える作業は思考力を伸ばします。実例ですが「1.3時間は何分?」という問題ができない女子がいました。「あのさ,1時間は何分なの?」と聞くと「60分」と即答してくれました。「じゃあ2時間は?」と聞くと「120分」とこれも即答。「いま何した?」「60倍した・・・あ,そうか!」。その子は1.3×60という計算をして78分と正解を出してくれました。1時間=60分と覚えているだけでは単位換算が身についているとは言えないのです。式をイメージして正しく計算する習慣が大切なのです。この式の場合,正しくは60×1.3です。60分の1.3倍ですから。でも筆算をするときは60×1.3=6×13よりも,1.3×60=13×6=78とした方が楽です。
「1.3時間は何分?」という問題ができなかった彼女は,第1志望は残念でしたが,吉祥女子中に合格し,そのまま高校に進学,2浪しましたが都内の大学の医学部に合格しました。今は海外研修に出かけるなど頑張っているようです。すごい・・・。