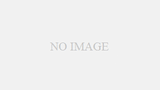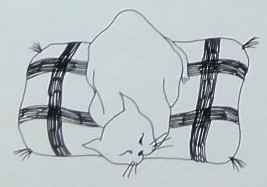
計算力を上げるには,計算の工夫も大切です。基礎的なものでは<例1>のような足し算があります。一の位での和を10にするという,小学校低学年で学習するものです。引き算の工夫も紹介します。<例2>のような引き算は筆算をするのが安全ですが,100を引いた後で引きすぎた数を足すという工夫で暗算をすることができます。
<例1> 28+35+44+15+12+36=28+12+35+15+44+36
=40+50+80=90+80=170
<例2> 325-98=325-100+2=225+2=227
足し算と引き算が連続している問題と,かけ算とわり算が連続している問題でも計算の工夫ができます。2つの例を示します。まず<例3>では,引き算を先にやる方法があります。足し算を先にやると数が大きくなってミスが出る可能性があるので,引き算を先にして数を小さくしていきます。足し算と引き算を別々にまとめる方法もあります。
<例4>のようにかけ算と割り算が連続している場合は,わり算を先にやって数を小さくすると計算が楽になります。足し算と引き算が連続している問題では,計算の順番をどのように変えても答えは同じですが,かけ算とわり算が連続している問題では,<例5>のように,かけ算を先にできない場合があるので要注意です。分数を利用するとこのようなミスはなくなります。次回は分数についてです。
<例3> 154+278+29-132-75=154-132+278-75+29=22+203
+29=254
<例3> 154+278+29-132-75=(154+278+29)-(132+75)
=461-207=254
<例4> 42×8÷5×15÷7=42÷7×8×15÷5=6×8×3=48×3=144
<例5> 3÷2×6=3×6÷2=3×3=9(正) 3÷2×6=3÷12= 4分の1(誤)

プロフィールと最近の投稿はサイドバーで。挿し絵はすべて自作したものです。