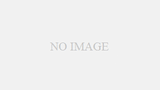切り絵 「○○大師と待ち合わせ」
切り絵 「○○大師と待ち合わせ」
答え合わせをしない子シリーズの最終回です。
中学生になっても宿題の答え合わせを自分でしない子がいます。それは,中学受験の段階で勉強方法に何らかの問題があったからだと思います。「勉強=ただ答えを書くこと」という姿勢があるのです。
中学受験では,週に3~4日塾に通うのが相場だと思いますが,主に算数の宿題が出されるはずです。その宿題をきちんとこなしているかのチェックは,塾の先生や親によって行われます。チェックが厳しすぎると,子供は叱られることを避けるために仕方なく宿題をやっています。このような子たちにとって,宿題とは自分の理解度や欠点を確認するためのものではなく,単なる苦痛を伴う作業と認識されています。
つまり,苦しい作業は早く終わらせてしまえばよいわけで,できたのかどうかはどうでもよいのです。間違っていた場合にはやり直しをすればよいのですが,できていないことをうるさく言われることが多いと,自分で答え合わせをする子でも,合っていない答えに○をつけてごまかしてしまいます。また,「分かったの?」と何度も聞かれると,その場から逃れるために,あまり自信はないのに「分かった」と答えてしまう子もいます。したがって学力は伸びず,定期テストでは親の期待に背くような結果になるわけです。そこで親はこう考えます。「もっと管理しないとダメだ」。ますます,子どもは自分で答え合わせをしなくなります。
答えあわせを子供にまかせ,その結果だけを親が見ているのではダメだと親が考えがちなケースには,入試問題の演習があります。子供が自分で採点し,その結果を親が見たとき,「これはできすぎでは?」と感じたときです。そこでは親は子のカンニングを疑っています(問題集には答えが付いています)。答えを見ながらやったのではないか?という疑念です。すると,次には解答を取り上げ,子供に入試問題をやらせた後の答え合わせは親がするようになります。確かにカンニングというケースもあるでしょうが,そうなるのはできの悪いことへの厳しい言葉が日頃からあるのが大きな原因です。基本的には答え合わせは自分でやらせ,やり直しまでさせるべきです。どうしても分からないものは質問をさせればよいのであり,できていることを要求しすぎてはいけません。